教員として働き続けていざ転職となったとき、必ず聞かれるであろう質問がこれまでの実績について。
普通に受け答えするのであれば、
- 売上を◯%上げることに貢献した
- ◯円の受注を成功させた
などの数字を交えつつ、これまでの実績について面接で話すことになると思います。
しかし、教員はどうでしょうか。
数字として語れる実績というのは少ないと思います。
教員という働き方自体が数字に囚われることなく、目の前の子どもの一生懸命向き合うという仕事なので、どうしても数字とは相性が悪いです。
ですが、そんな教員でも転職に役立つ数字や実績があります。
それがSNSです。
今回はブログとYouTubeがきっかけでスカウトされて転職した僕が、どのような点が企業から評価が高かったのかも含めて解説をします。

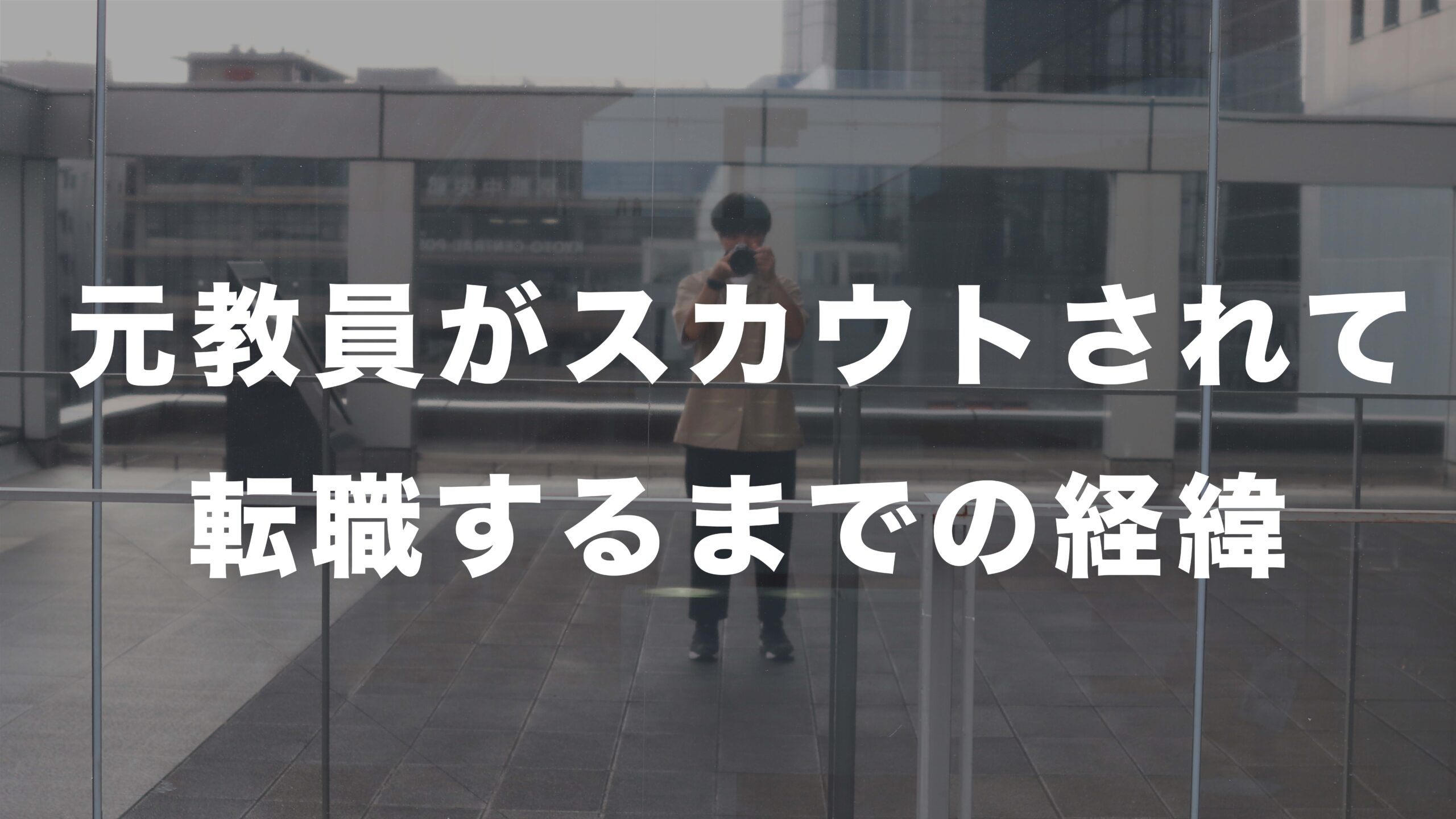
教員の実績は評価されにくい

はじめにも書かせてもらいましたが、教師の実績は評価されづらい傾向にあると思います。
実際に僕もスカウトされて転職用に職務経歴書を書いたのですが、出てきた実績としては
- 生徒に寄り添った指導
- 教科指導への取り組み方
- 体育祭などの大型行事のチーフをしたときの話
- 学校にアプリを導入した経緯
基本的には数字で表せることではなく、変化や結果を言語化することはできても数値化して伝えることは難しかったです。
もちろん職場内では上記の項目は評価され、年度末の評価はA判定をいただくなど、努力が結果としては表れていますが、それをどう企業が認めてくれる形で伝えるのかというところは課題でした。
SNSが実績になる時代

そんな企業に教員としての実績が伝えにくい中、何を評価してもらって転職に繋げたかというと、SNSです。
この2つのコンテンツ制作について評価をしてもらいました。
趣味で続けていたブログとYouTubeだったのであまり意識をしたことがなかったのですが、これらの作り上げた記事や動画というのは立派なコンテンツであり、作品。
つまりデザイナーなどが就活のときに企業に持っていくようなポートフォリオとしての機能が生まれます。
また、PV数やチャンネル登録者数など、
- どれくらい集客をすることができたのか
- どのような施作を実施して結果に繋がったのか
など、制作をしていく上で切ってもきれない関係のユーザー周りの問題やSEOの知識や対策なども実績として評価の対象です。
教員のコンテンツ制作力は高い

教員に共通する強みとしてコンテンツの制作力があると感じています。
毎日授業を考え、生徒に合わせたプリントを作成するなど、365日何かを生み出し続けている先生という仕事。
こんなに生徒に向き合ってきているわけですから、コンテンツを作り出す力が低いわけないと思います。
ブログやYoutubeを運営していく場合、記事や動画を生徒向けの授業資料のように思えば比較的簡単作れるのではないでしょうか。
最初に導入を入れて、展開として要点を詳しく、そして最後にまとめをする。
僕の記事や動画も基本的にはこの構成です。
授業を作るいつもの流れで制作をすることができると思います。
YouTubeをおすすめする理由
特におすすめする媒体はYouTubeです。
正直僕の転職に大きく関わったのはブログよりもYouTubeだと感じています。
転職が1番大きな変化ではありますが、その他にもたくさんの変化がYouTubeにはあったので、紹介します。
動画媒体の影響力が上がってきた

皆さんは最近わからないことがあったとき、Google検索とYouTubeの動画検索、どちらの方が多くなってきましたか?
最近僕は動画で調べることが多くなってきたような気がします。
もちろんまだ文字媒体の方が詳しく解説している領域もあるのですが、動画の検索ボリュームもかなり増えてきました。
知りたいことが動画で出てくる量が増えてきたように感じます。
そしてこれは本当にそうで、学校にいるとき生徒たちを見ていても基本調べ物はYouTube。
YouTubeになかったら渋々文字検索という流れ。
子どもも自分も含めて、だんだんと動画中心の生活に以降してきていると思います。
そうなると検索される回数が多い方で勝負をした方が、視聴回数や認知度が上がるというもので、ブログよりも早く実績が出る可能性があるということです。
実際に僕は5年続けてブログの月のPV数が3万超えがやっとなのに、YouTubeは2ヶ月目で月間10万回再生されました。
媒体によって回数の価値は違うとは思いますが、桁が違いすぎて驚きました。
登録者数が少なくても案件が来る

実際に始めてみて驚いたのが、登録者が少なくても案件の依頼がくること。
当時僕のチャンネルは100人くらいしかいなかったのですが、ソフトを試して欲しいとかマイクのレビューどうですかとか、様々な依頼メールがきました。
ブログの方は1~2ヶ月に1回くらいよくわからないデータ保存ソフトのレビュー依頼とかがくる程度で、大したことなかったのですが、動画を始めてからは一変。
100人のときで月に1回くらい、500人のときは週に1回くらいメールがきました。
再生回数的には1本だしても500回以下が多くて、5本に1本2~3000回、10本に1本1万回近くまで行くときがあるくらいで、影響力や再生回数はあまりない状態です。
それでも依頼がくるんです。
ブログのときにあまりこなかったときのことを考えると、動画の強さと企業の期待値が高いということがわかりました。
コンテンツの数と継続力を企業に評価してもらえる

これは転職の面接のときのことですが、1年間で50本の動画をアップしたことを褒めてもらいました。
だいたい週1のペースになるのですが、このコツコツと積み上げて継続し、それがわかる形で記録として残る。
このアップした本数というのは自分が継続してきた証なわけで、しっかりとコンテンツ制作に向き合っていることがわかる動画であれば、再生回数のような数字はあまりなくても、継続力の証明になります。
やってきたことが1つ1つ残っていくという点がYouTubeの魅力だと感じました。
合わせてブログもおすすめ
YouTubeだけでも忙しいと思うので、必須ではないですが個人的には合わせてブログも運営してしまうことをおすすめしたいと思います。
いまやYouTuberはブログから撤退している人も多いのですが、YouTube運営とは親和性が高いと感じているのでメリットが多いです。
原稿は必要になる

YouTubeの動画を撮るときは最低限原稿は作った方がいいと思います。
セリフを詳細に書く必要はないですが、テーマは何で、メインの話、流れ、まとめ、のような。
何も計画せずに話すと話がまとまらない他に、撮影時間が長くなって編集が大変になります。
つまり動画を短くして撮影した内容をまとまりのあるものにするためにはある程度の原稿が必要になるということで、このとき僕が原稿として読んでいるのが自分のブログです。
10分話すだけでもそこそこの知識量が自分にないと話せないというのは教員である皆さんであれば痛いほどわかることでしょう。
そうなると話すには原稿がいる→原稿をつくっているならそれをブログとしてアップしてしまう。
こんな黄金ルートが生まれるわけですね。
だから僕の動画の内容というのはもうすでにブログに上がっていて、それを後日動画化するという流れをとってきました。
YouTubeの写真を使って制作

僕の場合はブログを完成させてから動画でしたが、逆でも効率的です。
ブログには写真を載せた方が記事が華やかになって読みやすいので、なるべく写真を入れるようにしているのですが、原稿段階だと写真がありません。
ブログ用に写真を撮ってからYouTubeの撮影をすると二度手間に感じますよね。
であれば、原稿を作ってすぐ撮影をして、撮影した動画をスクショすれば動画も撮れてブログ用の写真の撮影も終了です。
実際に僕も素材がないときはYouTubeの動画を切り抜いてブログに使っています。
また、散財TVなおしまさんのブログもYouTubeのスクショを使ってブログを書いています。
このように動画さえあればブログ用の写真も兼ねることができるので、あとは少しアップまでの手間がありますが、大筋が同じなのでここまでそろっているならアップした方が得なように感じてしまいます。
X(旧Twitter)/インスタでもOK

もちろん集客ができる、コンテンツを積み重ねるという要素は同じなので、X(旧Twitter)やインスタでもOK。
ただこの2つのSNSは比較的短い文章や画像1枚で伝えたいことを伝え切るということが重要になってくるので、与えられる情報が少ない分かなり考えてコンテンツを制作していかないとなかなか人に届かないと思います。
僕はキャッチコピーやバナー作りが苦手だったので、長くはなってしまいますがブログとYouTubeを選びました。
面接で評価されること
いろいろ書いてきたので最後にまとめておきます。
僕自身が面接で評価されたことは
- コンスタントにコンテンツを投稿していたこと
- 長期間にわたって継続していたこと
再生数やチャンネル登録者数に関しては少なかったので実績とまではいきませんでした。
ですがもちろん、
- チャンネル登録者数
- フォロワー数
- PV数
など、はっきりとわかる数字も実績になります。
むしろチャンネル登録者数とフォロワー数が高ければ年収を大幅に上げる転職する視野に入ると思います。
SNS運用に関してはチャンネル登録者数とフォロワー数などの数字はあればあるだけ良いですが、なくても実績につながる部分はあるので、継続が大事だと感じました。
まとめ
SNSは日々の投稿をするだけのツールくらいの印象だったのですが、今や自分の実績として認められて仕事につながるツールにまでなってしまいました。
気軽に始められるので誰でもいつからでもチャレンジできるのが魅力ですね。
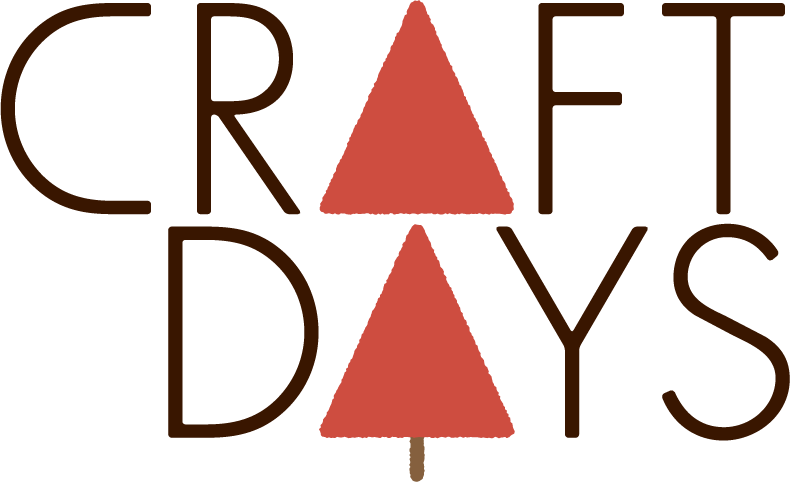







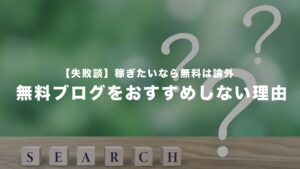
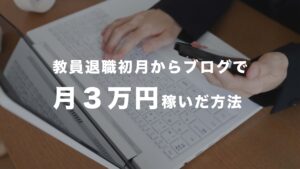
コメント