教員から転職をするということで、どんな準備をしておけば良いのかというのは気になるところですよね。
自己理解や面接対策など、実践的なことや転職までにやらなくてはならないことなどはたくさんあるのですが、とりあえずしておいて損はない準備が1つあります。
それはSNSの運用です。
ここで指すSNSはXやInstagram、Youtube(はちょっと入るか怪しいですが)などのことだと思ってください。

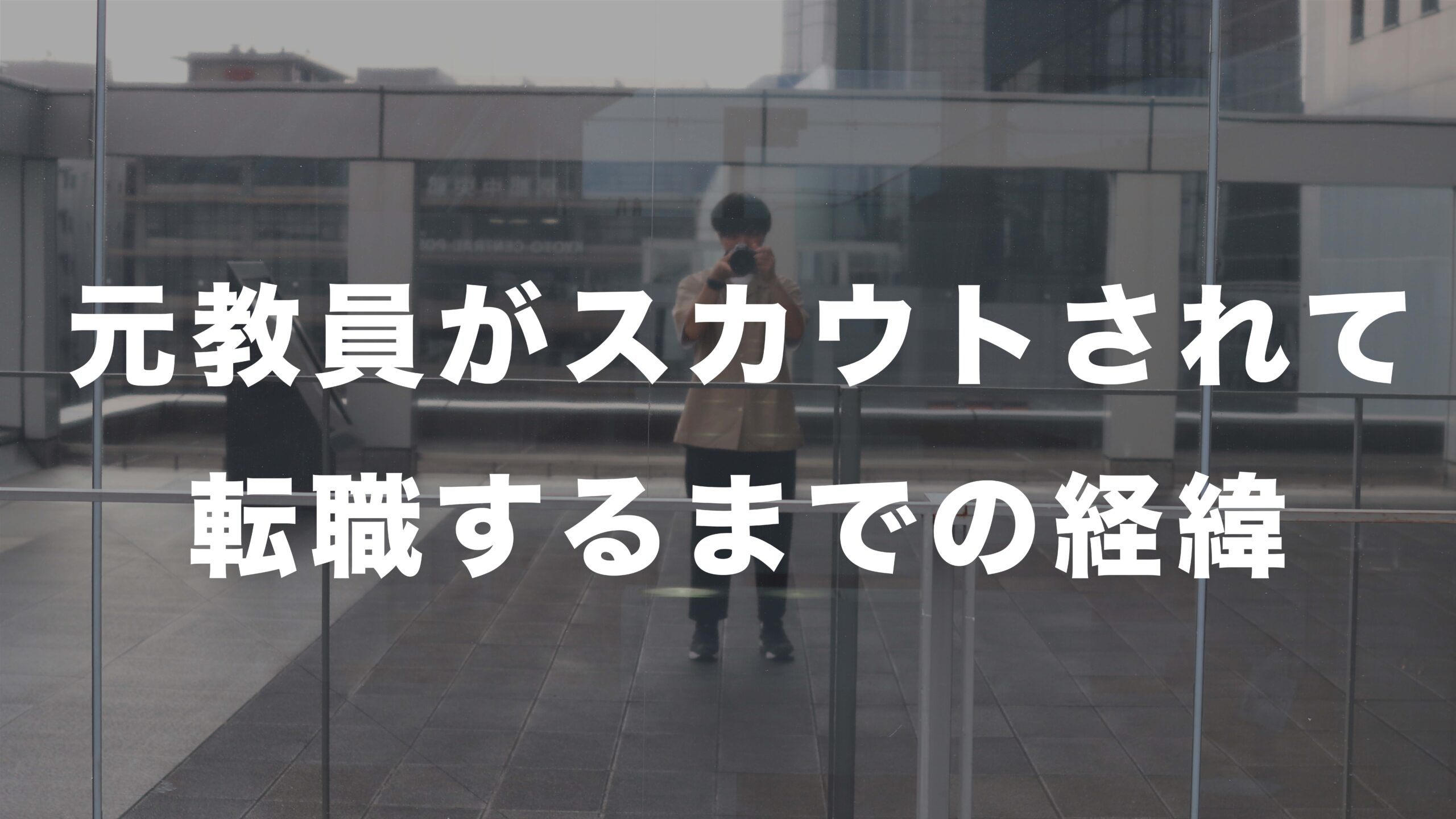
転職予定の会社で求められている実績を持っているのか

教員にとって転職のときに1番難しいポイントがここだと考えています。
それは転職先の会社で求められている実績や資格を持っているのかということ。
基本的に教員という経歴を評価されて転職できる職業は少ないと思います。
教員を評価という点では、教員免許が優遇される放課後等デイサービスくらいでしょうか。
求人を見ていると「法人営業経験⚪︎年以上」「WEB開発の経験」「⚪︎人以上のチームを運営」など、要項を満たせない求人が数多くあります。
そうなると未経験OKの求人しか選択肢に残らないわけですが、それだと転職はできるものの、年収や待遇が大幅に下がることがほとんどです。
SNSが実績として評価される時代

自分自身もかなり驚きの感覚なのですが、令和の現在、SNSが就職に繋がることもめずらしくなくなっているようです。
XやInstagramというのは知り合いの投稿や自分に必要な情報を得るために見るものであり、自分の使用方は交流のみ。
そんな感覚でいたのですが、現在はフォロワーの多さや投稿の内容はある種の実績と評価され、SNSを通じてスカウトされることや面接で武器として使える場合があります。
Youtubeがきっかけでスカウト
事実僕も、今現在の仕事は教員時代に趣味で運営していたブログとYoutubeをきっかけとし、Xから見つけてもらってスカウトしてもらいました。
趣味で続けていたことが仕事になった瞬間です。
コンテンツを作って誰もが見れる状態にしておくということは、ポートフォリオを所有しているような状態になり、自分の実績として活用することができるようになります。

教員から年収アップで転職
この動画で対談している方は教員から年収アップで転職をしたそうです。
気になる年収アップで転職が成功できたポイントはXのフォロワー数とのこと。
在職中からXでの発信活動をしていて、転職活動時には1万人を超えるフォロワーがいた状態だったようです。
この1万人のフォロワーをどのように集めたかなど、集客についてやコンテンツについてのことなどを面接で話した結果、年収アップでの転職に成功しました。
このように未経験であってもSNSが自分のポートフォリオや実績となって、年収や待遇アップの根拠として活用できて、成功に繋がるようです。
SNSを運営するメリット
事例を出してきたので、具体的にSNS運営にどのようなメリットがあるのかを解説します。
希望の仕事への理解が深まる

転職の準備のためにSNS運営をするということは、転職したい分野に関連する内容の運営をすると思います。
そして、その分野でファンをつけてフォロワーを増やすとなると、分野に対しての知識が必要になるはずです。
もともと好きだったり趣味だったりして、すでに知識はあるかもしれませんが、発信をするにあたってより調べてコンテンツにしていく過程でさらに知識が深まっていきます。
また、SNSでは発信内容を見てコメントをしてくれる人が出てくるはずです。
このコメントがありがたく、ときには自分よりも詳しい人が最新の情報を教えてくれることや自分では気が付かなかった視点の意見をくれることもあります。
自分を中心にコミュニティーができることで、発信内容の情報が自然と集まって自分の理解度も日々高まります。
フォロワー/登録者数が実績に

フォロワー数や登録者数は自分の投稿を見てくれる人の数、というシンプルな認識に留まらず、自分の実績として大きく貢献してくれる時代になりました。
自分のアカウントにフォロワーが多いということから集客の力や広告としての価値が生まれます。
特に集客の力というのは転職の際にも大きくアピールできるポイントになるはずです。
漫然と運営をしているだけではフォロワーは増えず、増やすには少なからず戦略があると思います。
その発信内容や戦略について、フォロワー数とともに数字で照明しつつ、具体的な言語化ができれば実績として評価されます。
転職後はそのまま副業として活用

実績作りのためだけではなく、副業としての可能性もあります。
人が集まり、投稿を見てくれる人が多いということはそれだけで収益を発生させる手段が多数生まれます。
例えばシンプルにX(旧Twitter)やYoutubeであれば、Postを見られて数(インプレッション数)や再生回数に応じて広告料をもらえる仕組みがプラットフォーム内に実装されています。
つまり、フォロワーや登録者数が多いということは、Postをする動画を作るという行為だけでもお金が発生するようになります。
また、Amazonのアフィリエイトリンクやフォロワーの多いアカウントには企業案件も来るはずです。
これらを活用することで、アカウントを起点として副業として成立させていくことができます。
SNSを運営して考えられる進路
では、実際にSNSを運用することでどのような職業に転職できるのかを考えていきます。
発信内容の分野への転職
僕の転職はこれに当てはまります。
ガジェットについて発信をしていたら、ガジェット関係のコンテンツ制作を担当する仕事にスカウトされたという感じです。
発信を続けていく中で、発信内容と同じ分野の企業からコンテンツ制作や関連の仕事にスカウトされたり、自分のアカウント運用を実績として面接で評価してもらったりして転職するというのはわかりやすい事例だと思います。
Webマーケター
インフルエンサーの方でも、自分のアカウント運用を活かしてWebマーケターに就職している方がいました。
Webマーケターとは大まかに仕事内容を整理すると、Web上での集客についての専門家。
つまり、アカウントを運用して大勢のフォロワーを個人で獲得できるような人は適正のある仕事だと言えます。
アカウントを伸ばすためには避けては通れない、キーワード選定やクリック率の確認、投稿内容の精査など、個人でこれまでやってきたことを企業規模で行なっていく仕事です。
もちろん個人の発信と企業の仕事は違うと思いますが、個人でも戦略を立ててWeb上で運営をしてきて成功した場合にはWebの集客についての進路が見えてくると思います。
SNS運用系のコンサル
これも運営に成功した人で仕事にしている人が見受けられます。
また、転職の求人にもSNSの運用コンサルという仕事も見かけるようになりました。
時代的にSNSの力が上がってきているからこそ、SNSを伸ばしたいと思っている個人や企業は増えています。
ただ、何も方針がないままだとすぐに失敗してしまう可能性が高いです。
だからこそ、個人で成功してきたという実績があれば、今度はコンサル側として仕事をしていく可能性が出てきます。
発信活動をしていると意外と声をかけられる

まだ何もSNSを運用していない人にはピンとこないかもしれないですが、運営をしていると意外といろんなメールがきます。
僕がこれまできたメールだと、ブログの売却をしないかというメールやガジェットのレビュー依頼、新作ソフトの無料体験や企業転職のスカウトなど、意外と人に見られているということを実感しました。
僕自身この記事を執筆時点ではSNSアカウントのフォロワー自体は少なく、Youtubeの登録者数が600人くらいといったところ。
それくらいのアカウントでもかなりの頻度で仕事の依頼がきます。
今後チャンネルが育ち、他のアカウントが伸びていったらさらに案件やメールは増えていくと思います。
もちろん大きいアカウントの方が仕事の規模や料金も大きいと思いますが、少ないからといってこないというわけではないんです。
発信活動はノーリスクハイリターン

基本的に発信活動はノーリスクハイリターンだと思っています。
どのSNSアカウントも運営自体は維持費0。
もちろん作業時間は自分の自由時間を使うので失うものが何もないわけではないですが、お金については初期費用がかからないので失うものも在庫を抱えることもありません。
アカウントの運営が上手くいかないなら気軽にやめてしまったとしても特にダメージはなし。
そう考えると、失敗しても失うのは作業時間くらいでお金ではなく、成功したら青天井というのは誰にでも始めやすい準備だと思います。
起業とか物販とかになると最低限必要になってくるお金があると思うのですが、SNSは必要なし。
失うもののリスクが(経済的には)少なく、成功すればラッキーくらいの感覚で始められるのは非常に安心です。
まとめ
僕自身趣味で運営していたYoutubeがこんなに評価されて仕事に繋がるなんて全く考えていませんでした。
しかもYoutubeを始めたことに関しては特に費用もかかってないので(ガジェット購入は趣味なのでカウントしません)、初期費用がかかって生活ができない、みたいなことにもなりませんでした。
SNSにはまだまだ可能性があると思うので、何か準備をして転職に臨みたいなら、転職したい分野のアカウントを育てることをおすすめします。
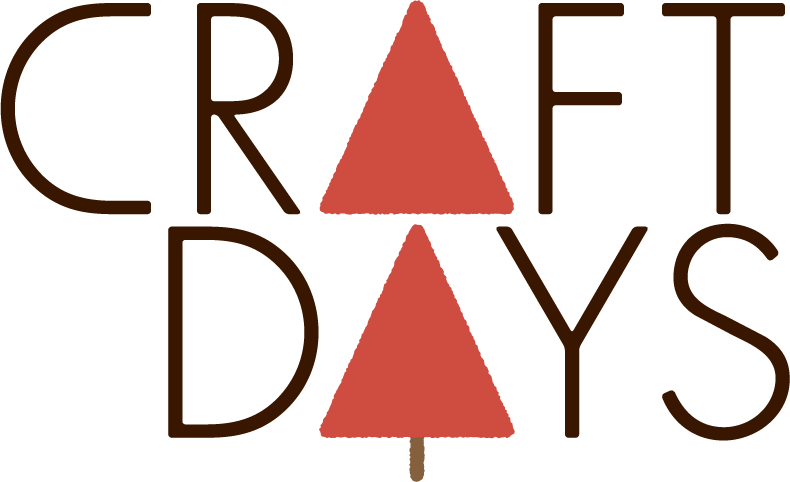
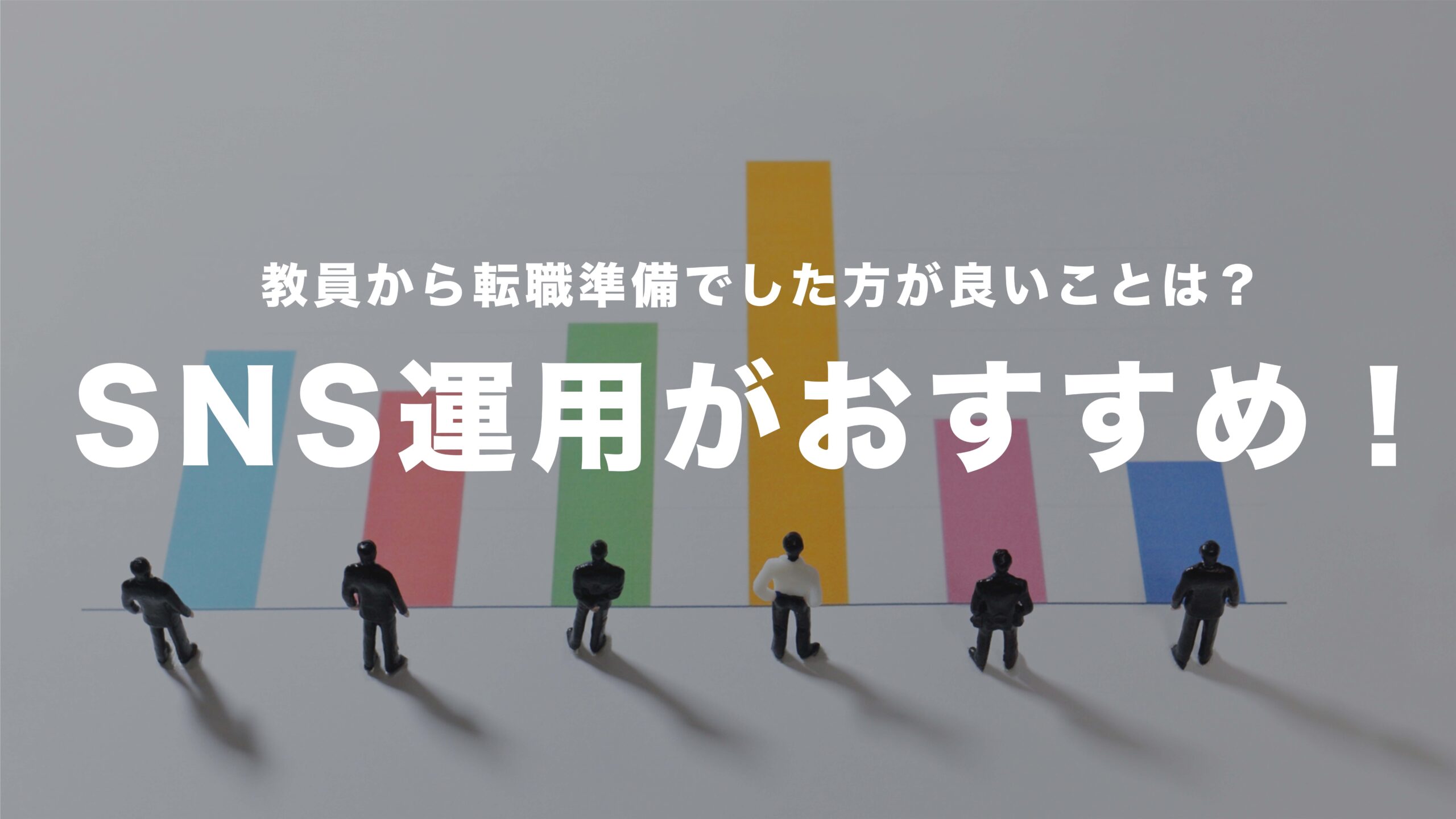


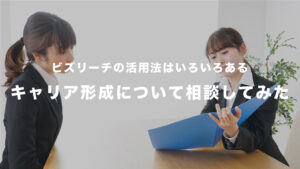





コメント